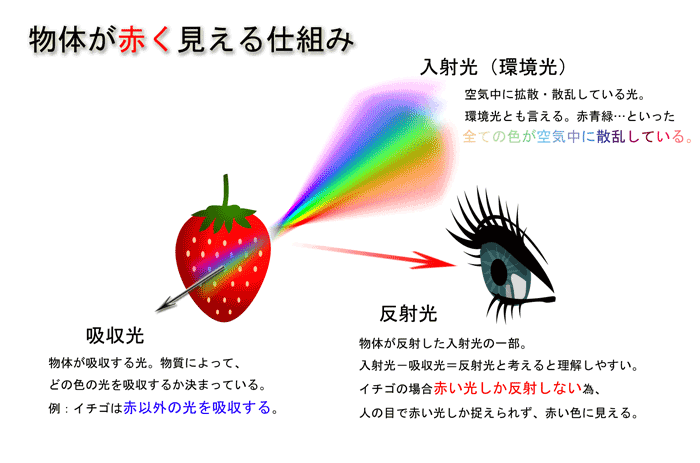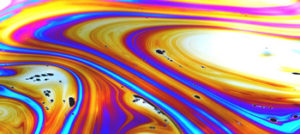『ゼロから始めるステイン講座 Ⅵ』
透明だけど透明感がない?
モノリシックセラミックスについての考察 ④
そろそろ臨床話が聞きたいんじゃい!
……もうしばしご辛抱下さいませ。
前回は加法混色と減法混色の差について、
模式図や動画を用いて解説しました。
とはいえ、実際の臨床とどの様に直結するのか、
まだピンと来ないと思います。
およそ次回あたりで
全容が見えてくると思いますが……。
もう少し色彩学の話が続きます。
今回は「補色」についての簡単な説明と、
「環境光の吸収と反射」について解説します。
●補色とは何か
簡単に言えば、相反する真逆の色です。
例えるなら「赤の反対は青」といった具合で、
各々の色に対応した正反対の色があるのです。
色彩学においてこれを「補色」と呼んでいます。
じゃあピンクの反対は?緑の反対は?
これに関しては「補色対比表」を
ご覧頂いた方が話は早いと思います。
なんだかカラフルな表ですね。
よく見ると、隣の色に移るごとに
グラデーションがかっていることが分かります。
この円を描くように並んだ色の、
その対極側にある色が「補色」なのです。
ちょうど赤の反対側に青がありますので、
赤の補色は青になります。
逆に言えば、青の補色が赤とも言えます。
ところで先程から赤だの黄だの言っていますが、
そもそも赤って何なのでしょう。
もっと分かりやすく言うと、
なぜ赤いものは
赤く見えているのでしょうか。
うーん?
●「赤以外の光を吸収する特性の物質」が
赤く見える
結論から言って、
赤く見える物体は、青や緑といった
その他全ての色の光を吸収し、
赤い光のみを反射する働きがあるのです。
模式図にまとめるとこんな感じです。
人間の目は、物体から反射した光、
つまり反射光を捉えることで
物体を視認しています。
イチゴは、赤色の光しか反射しません。
バナナは、黄色の光しか反射しません。
それ以外の全ての色の光は
物体に吸収されてしまいます。
つまり物質によって、反射できる光の色が
あらかじめ決まっているのです。
●環境光には全ての色が内包されている
ん?… ちょっとおかしいぞ?
緑や青の光を吸収するとか言うけど
そんなカラフルな光、
日常生活で見たことないよ?
……なるほど、確かにそのように思えますが。
実は目に見えなくても、
環境光に全ての色が内包されています。
環境光とは、例えば屋外なら太陽光、
室内なら蛍光灯の光と思ってください。
要は環境光=空間を満たしている光のことです。
しかし全ての色が内包されているなら
部屋中が虹色な空間になりそうなものですが、
そうはなっていませんよね。
何故なのでしょう。
ここで思い出してほしいのが、
前回説明した「加法混色」です。
なるほど!
環境光には
あらゆる色光が混ざり合っているが故、
白色(無彩色)と化しているのです。
ちなみに「プリズム」を介することで
環境光に内包された全ての色は
分解され、
初めて視認できる様になります。
[wikipediaより抜粋]
七色で大変綺麗ですね。
●まとめ
環境光はあらゆる物体へ入射しますので、
入射光とも呼べます。
まとめると、
環境光(入射光)は
全ての色を内包している故に
無彩色光ですが、
イチゴは赤い色の光以外を吸収するので
赤い光しか反射せず、
反射光が赤くなるので、
人間の目には赤く見える。
ということになります。
以上です。
次回は
「ゼロから始めるステイン講座Ⅶ」
透明だけど透明感が無い?
モノリシックセラミックスについての考察⑤
へ続きます。
いよいよ臨床的な内容になってきますので、
乞うご期待。
【過去の関連ブログへのリンク】
~気になるステインの選び方~
~内部ステインと
外部ステインのコンセプト~
透明だけど透明感がない?
モノリシックセラミックスについての考察 ①
透明だけど透明感がない?
モノリシックセラミックスについての考察 ②
ライター 髙瀬 直