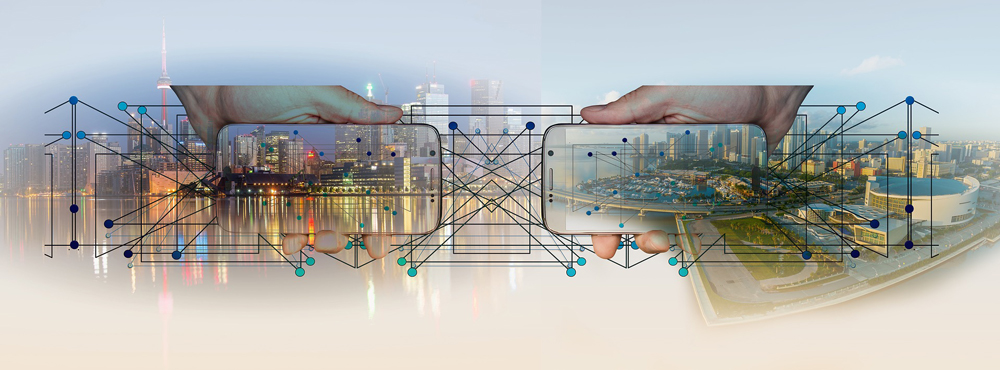「最近?手に入れた便利アイテム」
弘法は筆を選ばず、とはよく言ったものですが。
これはあくまで
「筆が多少ダメでも
一定以上は実力でカバーできる!」
という意味であり。
「筆の良し悪しに関わらず最高の作品が作れる!」
などといった意味では決してありません。
歯科技工士も歯科医師も基本的には技術職です。
扱う道具一つで、
作業効率や結果が大きく変わることもあります。
もちろん、一つの道具を長く使い続け、
熟練することも大切です。
しかし、常に新しい物にアンテナを張り、
従来品より優れた品があれば直ちに取り入れる。
そんなドッグイヤースタイルもまた、
大事なのではないかなと思ったりします。
というわけで今回、最近私が使うようになった
道具や材料について四点ほどピックアップし、
自分なりに使用感や特徴をまとめてみました。
スキャンコート:
(株)アネロクラシックさんの模型硬化剤です。
光を反射しやすかった従来の模型硬化剤の
欠点を克服し、スキャン精度を向上させた一品。
すでに多くの方がお使いの上、評判が良さげなので
小社でも取り入れてみました。
(迅速に手配して下さいました河田様、
誠にありがとうございます!)
なるほど、確かにスキャンパウダーがいらぬ……!
以前からずっと、パウダーの厚さ分だけ
適合が緩くなるのが気掛かりだったのです。
でもこれがあれば、
快適なスキャンライフが送れそうですね。
ただ、石膏トリマー使用前に
硬化剤を使用している場合は
層が厚くなり易く、注意が必要です。
その他、スキャンコートを塗布した模型に
グルーガンを使用すると、
皮膜とグルーが融合してしまう場合があります。
特に支台歯へのグルー付着には
重々気を付けましょう。
使い捨てマウントホルダー:
これはマグネット用の使い捨て「座金」です。
従来品と同様、咬合器マウントに使用します。
こちらもスキャンコートと同じく、
(株)アネロクラシックさんの製品です。
お値段にして1枚あたりおよそ5.4円(税込み)。
たった10.8円で上下のマウントができちゃいます。
仮に従業員の時給が1,200円だとすると、
1分あたりのランニングコストは20円。
マウント石膏を砕いて座金を回収するのに、
上下で33秒かかるとしましょう。
その場合のランニングコストは11円です。
つまり上下の座金回収に33秒以上かかるなら、
これだけで元がとれてしまいます。
しかも常に新品を使えますから、
サビたり傷がついたりして
維持力が落ちる心配もありません。
模型をマウントしたまま納品し、そのまま座金が
医院様から帰ってこない場合も問題なし。
使い捨てタイプなので、
あまりエコではない一面もありますが……
そもそも座金は消耗品です。
定期的に買い替えるコストを考えれば、
使い捨てタイプは数値以上にコスパに優れます。
さらに石膏粉砕の際に粉塵が舞ったり、
ごみが散らばることもありません。
模型からマウント石膏を外したら、
そのままゴミ箱へポイというのは気が楽です。
是非お試しあれ。
ZirGloss:
(株)松風さんの対ジルコニア用研磨剤です。
比較的切削力が高く、それでいてマットな光沢を
再現しやすいので重宝しています。
使用感として、他社製品と比較して
極端な有意差は無いものの、切削力においては
頭一つ抜けている印象があります。
即重くらいならレーズの砂研磨ぐらいのノリで
面を慣らすことができますので、
セラミックス以外でも広く応用して使っています。
名称がZirGrossだったら完璧だったのですが、
欲張りすぎでしょうか。
シャープペンシル:
……え?筆記用具っすか?
そんなこと言わずに聞いてください。
主にジルコニアフレームの
厚さ調整に使っています。
もちろん、ジルコニアフレームは
最低厚み0.5㎜を下回ってはいけない!
というのが定説なのですが……
臨床上、これが現実的でない場面があります。
ディープバイトの上顎前歯部補綴などにおける、
基底結節付近などが顕著ですね。
この時、シャーペンでフレーム内面を
真っ黒に塗りつぶすと、黒の透け具合で
フレームの厚さが容易に判断可能なのです。
逐一メジャリングデバイスで計測しなくても、
スピーディにフレーム調整が可能となります。
特にメジャリングデバイスの入りきらない、
前歯部の支台歯尖頭部分などにおいて優位です。
別にシャーペンではなく
黒マジックなどでも良いのですが、
下顎前歯のクラウンなどは支台歯が細すぎて、
奥までマジックが入りきらないことがあります。
従来はフレームを光に照らし、
その透過度で厚さを判断していました。
しかし眩しい上に非効率なので、最近では
もっぱら内面塗りつぶし法でやっています。
ひとまずこんな感じです。
何かの参考になれば幸いです。
ライター 髙瀬 直